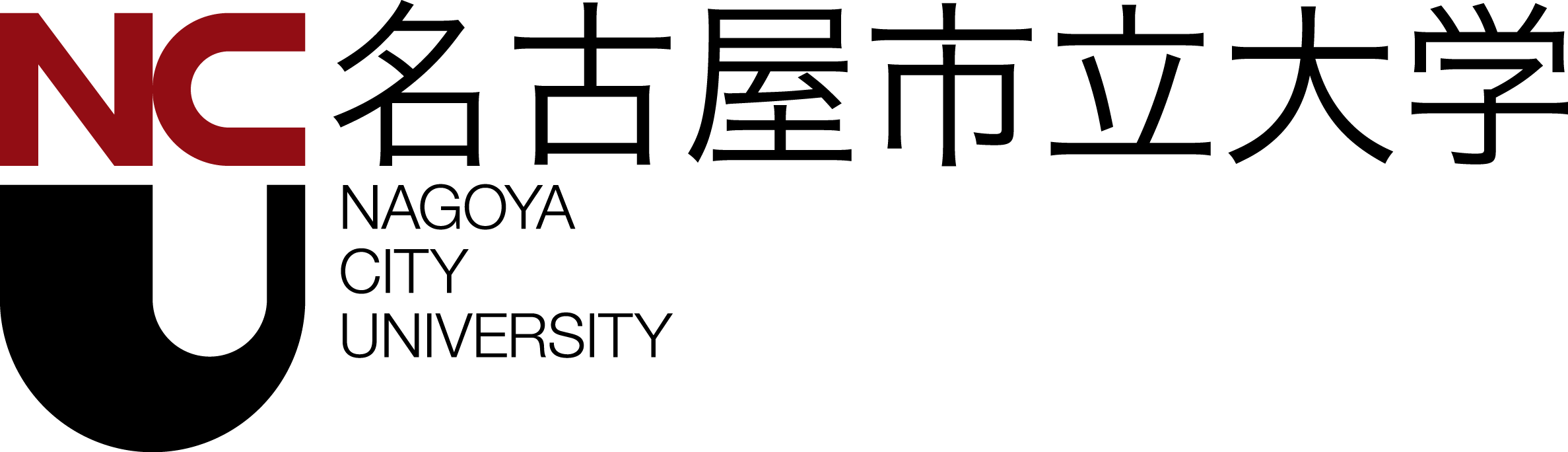研究者データベース
山中 亮 (ヤマナカ アキラ)
メールアドレス: yamanaka  hum.nagoya-cu.ac.jp hum.nagoya-cu.ac.jp | |||
Last Updated :2024/03/19
研究者情報
学位
J-Global ID
研究キーワード
研究分野
学歴
- 1996年04月 - 2001年03月 東北大学大学院 教育学研究科博士課程後期3年の課程
- 1994年04月 - 1996年03月 東北大学大学院 教育学研究科博士課程前期2年の課程
- - 1994年 東北大学 教育学部 教育心理学科
所属学協会
研究活動情報
論文
- Akira YAMANAKA; Kyoko TAGAMIAsian Journal of Human Services 21 18 - 28 2021年
- 北島 麻衣子; 大津 美香; 冨澤 登志子; 田上 恭子; 笹竹 ひかる; 井瀧 千恵子; 加藤 拓彦; 小山内 隆生; 米内山 千賀子; 漆坂 真弓; 山中 亮; 岩岡 和輝; 西沢 義子保健物理 52 2 61 - 67 (一社)日本保健物理学会 2017年06月
- Akira YamanakaOmega: Journal of Death and Dying 71 1 82 - 91 2015年
- 山中亮心理臨床学研究 31 6 999 - 1009 日本心理臨床学会 ; 1983- 2014年
- 山中亮自殺予防と危機介入 31 1 43 - 50 日本自殺予防学会 2011年
- 自殺で親を亡くした大学生に対する態度の検討-大学生を対象として-山中亮自殺予防と危機介入 30 2010年
- 自死遺族に対する大学生の否定的態度に関する研究山中亮臨床死生学 13 41 - 49 2009年
- 山中亮; 田上恭子臨床心理学 9 3 382 - 387 金剛出版 2009年
- 山中亮感情心理学研究 17 1 42 - 48 JAPAN SOCIETY FOR RESEARCH ON EMOTIONS 2009年
- ネグレクトのアセスメントスケール作成の試み三上邦彦; 山中亮; 久保順也子どもの虐待とネグレクト 6 70 - 77 2004年
- A YamanakaPSYCHOLOGICAL REPORTS 92 1 153 - 160 2003年02月
- 性非行についての一考察-児童相談所における相談事例を対象に-浅野晴哉; 山中亮; 菊池武剋東北児童青年精神医学会機関誌 2 26 - 29 2002年
- 山中亮感情心理学研究 6 1 27 - 36 JAPAN SOCIETY FOR RESEARCH ON EMOTIONS 1998年
- 大学生における自死遺族に対する態度と自殺観,死生観との関係山中亮Asian Journal of Human Services 2 38 - 50
MISC
- 主体的に生きることの難しさ―野首論文へのコメント―山中亮 岐阜大学心理教育相談研究 (21) 31 -33 2022年04月 [招待有り]
- 山中亮; 久保田健市; 天谷祐子; 伊藤亜矢子; 小川成; 坪井裕子; 中川敦子; 山本竜也 日本心理学会大会発表論文集 85th 2021年
- 青年期における故人との絆のあり方ー親との死別を体験した大学生の絆に関する主観的体験ー山中亮; 田上恭子 名古屋市立大学医療心理センター臨床心理相談室紀要 (1) 1 -16 2020年02月
- 田上恭子; 山中亮 日本心理学会大会発表論文集 84th 2020年
- スクールカウンセラーの今後のあり方について―外部性と予防的介入に注目して―山中亮 平成30年度基本方針「なごや版キャリア支援」策定委託事業調査・研究報告書 115 -126 2019年03月
- 山中亮; 田上恭子 日本心理学会大会発表論文集 83rd 2019年
- 田上恭子; 山中亮 日本心理学会大会発表論文集 83rd 2019年
- 山中 亮; Yamanaka Akira 北海学園大学経営論集 15 (3) 61 -69 2018年03月
- 山中亮; 田上恭子 日本心理学会大会発表論文集 82nd 2018年
- 田上恭子; 山中亮 日本応用心理学会大会発表論文集 84th 2017年
- 田上恭子; 山中亮 日本心理学会大会発表論文集 81st 2017年
- 山中亮; 田上恭子 日本心理学会大会発表論文集 81st 2017年
- 精神障がいのある親とその子どもの支援山中亮 北海学園大学学園論集 (139) 97 -105 2009年
- 山中亮 北海学園大学学園論集 135 (135) 31 -39 2008年
- 山中亮 北海道心理学研究 (29) 2007年
- 山中亮; 田上恭子 日本心理学会大会発表論文集 71st 2007年
- 抑うつ感情・不安感情と認知的失敗低減方略利用との関連-場面想定法による検討-山中亮 北海学園大学学園論集 (127) 71 -79 2007年
- 抑うつ傾向,不安傾向,認知的失敗低減方略の利用,認知的失敗の発生の関連性山中亮 北海学園大学学園論集 (131) 65 -71 2007年
- 山中 亮 学園論集 127 (127) 71 -79 2006年03月
- 山中 亮 北海学園大学経営論集 3 (3) 127 -130 2006年03月
- 田上恭子; 山中亮 東北心理学研究 (54) 2005年
- 学生相談におけるメール利用システムの現状-全国国立大学法人のウェブサイトの外形的調査から-佐藤静香; 山中亮; 池田忠義; 吉武清實; 仁平義明 東北大学学生相談所紀要 (31) 1 -4 2005年
- 山中亮 日本心理学会大会発表論文集 68th 2004年
- 山中亮 東北心理学研究 (53) 2004年
- 東北大学における学生支援としての予防教育池田忠義; 吉武清實; 仁平義明; 山中亮; 佐藤静香 東北大学大学教育研究センター年報 (11) 45 -54 2004年
- TAによる修学ピア・サポート-カウンセラーと工学部・工学研究科協働による修学支援の取り組み-山中亮; 吉武清實; 池田忠義 東北大学学生相談所紀要 (29号) 1 -8 2003年
- 新入生の大学生活に対する意識-学部ごとの特徴及び期待・不安に焦点を当てて-佐藤静香; 池田忠義; 吉武清實; 山中亮; 仁平義明 東北大学学生相談所紀要 (29) 9 -22 2003年
- 認知的失敗を低減するための方略利用の特徴について山中亮 東北大学保健管理センター年報(平成13年度) 19 -24 2002年
- 山中亮 日本心理学会大会発表論文集 65th 2001年
- 失敗低減方略と感情との関連について山中亮 東北大学教育学部研究年報 (49) 271 -280 2001年
- 山中亮 日本心理学会大会発表論文集 64th 2000年
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2018年04月 -2023年03月代表者 : 田上 恭子; 山中 亮本研究の目的は,死別への適応において故人との絆がどのように変容していくか,故人を想起する際の主観的体験と無意図的想起の機能に着目し明らかにすることである。令和3(2021)年度の計画は,第一にこれまでの研究成果について論文を投稿すること,第二に絆の概念の整理を行い尺度作成研究に向けて準備を行うこと,第三に絆の変容を質的に明らかにすることを目的とした面接調査の実施準備を行うことであった。令和3(2021)年度の研究実績は以下の通りである。 1) 先に調査を行った対象喪失と喪失対象に関する記憶の現象学的特性に関するデータについて,時間的経過及び喪失への適応と想起の特徴との関連を検討するために再度分析を行った。結果,喪失への適応に伴い現象学的特性が変化すること,特に想起時に強い感情を伴わなくなることが喪失への適応指標となり得ることが示唆された。本結果について,学術雑誌へ投稿した。 2) 故人との継続する絆の概念を整理し,全般的な研究動向と記憶からのアプローチに関して研究の現状と課題を整理するために,先行研究の文献検討を行った。現在レビュー論文を執筆中であり,令和4(2022)年度に学術雑誌に投稿する。 3) 継続する絆に関する尺度を翻訳し日本語版を作成するために,また絆と記憶に関する質問紙調査実施に向けて,文献の精読を行った。現在も先行研究の知見を整理しつつ,令和4(2022)年度の調査実施に向けて準備を行っている。 4) 故人との絆の変容プロセスを明らかにすることを目的として実施する予定の面接調査に向けて,まず研究法に関する学習と検討を行った。また先行研究の精読を行い,面接・分析の観点に関して検討を行った。令和4(2022)年度より面接調査を開始する予定である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2017年04月 -2023年03月代表者 : 山中 亮; 田上 恭子大切な人との死別は誰もが経験しうるものであるが,時に強い心理的衝撃を与えるライフイベントにもなり得る。本研究では,こうした死別に伴う悲嘆プロセスにおいて近年注目されている「継続する絆」概念を再検討することを目的とする。「継続する絆」のあり方には文化の影響が大きく反映することが想定され,欧米とは異なった「継続する絆」のあり方が日本にはあるのではないかと考えられる。 そこで,我が国において親密な人を喪った後に遺された人々は故人とどのような関係を築いていくのかを明らかにし,実証的検証に基づいた我が国における新たな悲嘆理論の構築を目指す。 まずは「継続する絆」についての概念分析を行い,「継続する絆」の形成・変容に関する仮説モデルを提案する。概念分析は,1概念を選択する,2分析の狙いまたは目的を決定する,3選択した概念について発見したすべての用法を明らかにする,4選択した概念を定義づける属性を明らかにする,5モデル例を明らかにする,6補足例を明らかにする,7先行要因と結果(帰結)を明らかにする,8経験的指示対象を明らかにする,の8段階から成っている。 昨年度は概念分析を行った結果に基づいて,仮説モデルを再検討した。それを踏まえて,先行要因に関する実証的検討を行う予定であったが,コロナ感染拡大の影響もあり,今年度実証的検討の実施はできていない。 今年度は,仮説モデルを精査して,実証的検討を行う予定である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2014年04月 -2018年03月代表者 : 田上 恭子; 山中 亮本研究は,故人を含む自伝的記憶が故人との継続する絆においてどのように機能しているかを明らかにすることを主たる目的とし,精神的健康,喪失体験の性質,継続する絆,故人を含む自伝的記憶の想起における主観的体験,及び故人の無意図的想起との関連について検討した。主な結果として,(1)精神的健康状態が良好な場合は必ずしも故人との絆が死別への適応を高めるわけではない可能性,(2)故人との絆には故人を含むエピソードのポジティブな感情を伴う想起が関連すること,(3)故人の無意図的想起頻度の高さは精神的健康状態の不良さと関連することが示された。今後故人の続柄別検討などさらに精緻な研究が必要である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2011年 -2012年代表者 : 山中 亮; 田上 恭子”故人との絆”とは近年悲嘆研究の領域で注目されている概念で,死別後も故人との関係が永続していると感じられることを指す。これは多くの日本人に受け入れられている考え方だとされているが,一方で都市化が進む中で受け入れられなくなっているのではないかという指摘もある。そこで,本研究では,故人との絆のあり方に地域風土がどのように影響を及ぼしているのかを明らかにするため,祖霊崇拝の風土が色濃く残る津軽地方及びそのような風土があまり強くないと考えられる北海道,それぞれ出身の学部学生に面接調査を実施した。その結果北海道地方に比べて津軽地方出身の学生では,故人との絆を認める傾向が強いことが示された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2003年 -2004年代表者 : 山中 亮本年度の研究では,抑うつ・不安傾向と認知的失敗低減方略利用頻度の関連について,抑うつ・不安傾向が方略に対する認知にどのような影響を及ぼしているかについて検討した. 【方法】 調査対象:質問紙に不備のあった者を除いたT大学学部学生210名(男92名,女118名)を分析対象とした. 抑うつ・不安測定:BDI(林,1988)とSTAI日本版(中里・水口,1982)によって抑うつと不安を測定した. 失敗低減方略利用頻度測定:失敗低減方略利用頻度尺度(山中,2002)を用いた.この尺度は,"外的記憶補助","記憶術","時計・携帯利用","指差し","確認"という5つの下位尺度から構成されている. 失敗低減方略利用頻度の認知:失敗低減方略利用頻度尺度について,6件法にて有用感(全く役に立たないと思う〜非常に役に立つと思う),コスト感(全く大変ではないと思う〜非常に大変だと思う)について評定させた. 【結果と考察】 群の設定:平均値を基準に,BDI得点が12点以上の者を抑うつ高群,11点以下の者を抑うつ低群とした.またSTAI得点が54点以上の者を不安高群,53点以下の者を不安低群とした. 抑うつ・不安傾向と失敗低減方略の有用感との関係:失敗低減方略利用頻度尺度の有用感について,抑うつ・不安を要因とした分散分析を行なった.その結果,不安高群が低群に比べて"外的記憶補助"を有用だと感じていることが明らかとなった.また低不安である時に抑うつが低いよりも高い場合に"指差し"を有用だと感じていることが明らかとなった. 抑うつ・不安傾向と失敗低減方略のコスト感との関係:失敗低減方略利用頻度尺度のコスト感について,それぞれ抑うつ・不安を要因とした分散分析を行なった.その結果,"時計・携帯利用","指差し","確認"いずれの方略においても,不安が低い時よりも高い場合に利用が大変だと感じるという傾向がみられた.
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2003年 -2004年代表者 : 菊池 武剋; 沼山 博; 福島 朋子; 山中 亮今年度はハンセン病療養所の実態把握と入所者との信頼関係の構築に努めつつ、数名を対象に面接調査を行った。それらを総合した結果は次の通りである。なお、これらの成果をInternational society for the Study of Behavioral Developmentや日本発達心理学会で発表した。 (1)人生(生涯)そのものに対する認識:現在の入所者の多くが児童期を過ごした戦争中はやはり国家主義的で、隔離されること自体が国に協力することに通じると考えられていた。終戦前後は、食糧難に、監視の強化がありまって、特に苦難な生活を強いられた。園内の民主化は社会よりもずっと遅れたが、患者の運動や社会啓発により、園内の施設や患者の待遇改善などが行われ、全体的に年を取るほど良くなってきたと考えられている。しかし、それはあくまで差別的な待遇に基づく表面的な措置であり、根本的な人間性の回復が必要だと考える人々もおり、それが国家訴訟の原動力となった。結果的に勝訴(国が控訴を断念)、名誉回復が決まったが、その喜びの反面、高齢化が進んで社会復帰が現実的には不可能な点を惜しんでいる人がほとんどである。 (2)社会に対する認識と社会的自己観:入所前野差別体験が尾を引き、現在もなお、園外の人々は明確な差別意識を持っていると考え、園外へ出ることを怖いと感じている。しかし、さまざまな交流で園外の人々への恐怖感は減っており、そういう恐怖を持つような偏見を社会に対して持っていたことと思う人々も出ている。他方で、社会復帰者に対する入所者の対応に見られるように「社会に出ること」の意味づけは非常に大きく、そのため逆に「社会に出られなかった」自らの人格や能力を過小評価する傾向がある。自己評価のための基準が園内にしか存在せず、社会の中でどんな位置づけにあるかを確認する機会に乏しかったことがその理由として考えられる。