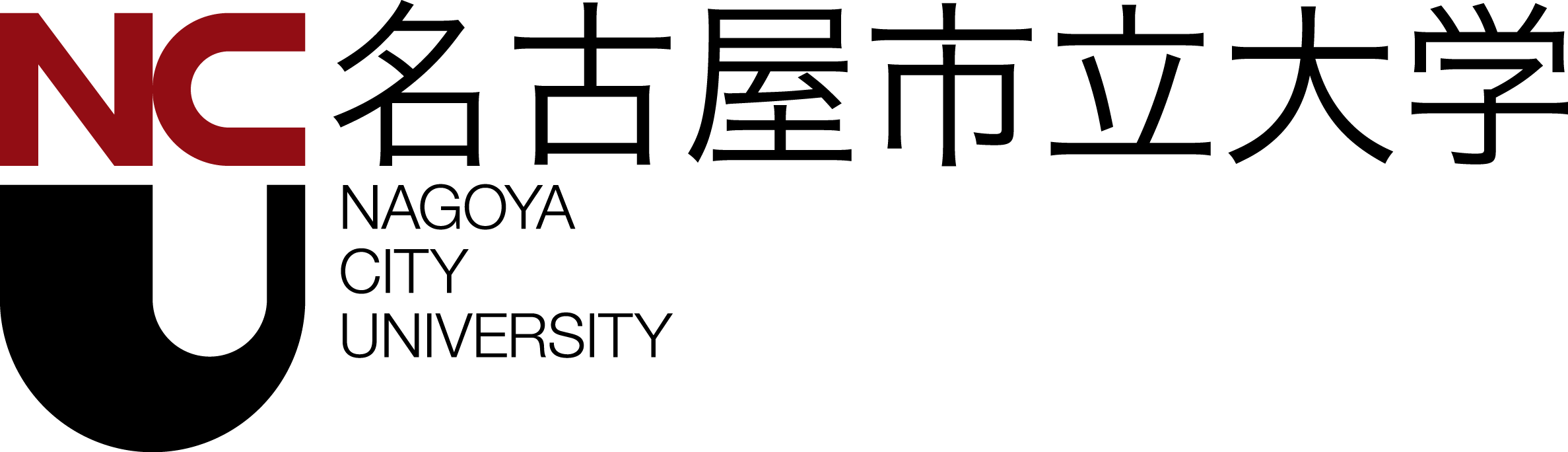研究者データベース
田中 正彦 (タナカ マサヒコ)
メールアドレス: mtanaka  phar.nagoya-cu.ac.jp phar.nagoya-cu.ac.jp | |||
Last Updated :2026/02/05
研究者情報
学位
ホームページURL
科研費研究者番号
- 60267953
ORCID ID
J-Global ID
プロフィール
これまでの研究〜現在の研究
1.神経研究に役立つ実験系の開発
① 小脳形成過程をin vitroで再現するスライス培養系の開発(Brain Res., 1994;神経化学, 2001)
② 単一細胞エレクトロポレーションを用いた培養神経細胞へのsiRNA導入法の開発(J. Neurosci. Meth., 2009;Neuromethods, 2012)2.小脳形成のメカニズム解明
① 小脳形成過程で起こる顆粒細胞死のメカニズム(Neuroscience, 1998)
② Notch2によるグリア細胞の分化状態の制御(J. Neurobiol., 1999)
③ プルキンエ細胞樹状突起の形成メカニズム
・受容体型チロシンホスファターゼPTPζ およびバーグマングリア細胞の関与(J. Neurosci., 2003;神経精神薬理, 2007)
・生細胞イメージングを利用した、一部の突起の退縮が起こることの証明(Neuroscience, 2006)
・リアノジン受容体の関与(Dev. Neurobiol., 2014)
・CaMKII & IVの関与(Neuroscience, 2021)3.小腸の恒常性と炎症における腸管グリア細胞の重要性
① 腸管グリア細胞におけるカルシニューリンの役割(Biol. Pharm. Bull., 2018)
② 腸管グリア細胞からの分泌物質の役割(Cells, 2023)
※小脳におけるグリア細胞の研究が、小腸の腸管神経系におけるグリア細胞の研究につながりました。
研究キーワード
研究分野
経歴
- 2007年 - 現在 名古屋市立大学大学院薬学研究科 生体超分子システム解析学分野准教授
- 1998年 - 2006年 藤田保健衛生大学総合医科学研究所 応用細胞学研究部門講師
- 2006年 名古屋市立大学大学院薬学研究科 生体超分子システム解析学分野助教授
- 1994年 - 1998年 藤田保健衛生大学総合医科学研究所 応用細胞学研究部門助手
- 1996年06月 - 1996年08月 Marine Biological Laboratory (Woods Hole, MA, USA)“Physiology: Cellular and Molecular Biology” course
学歴
所属学協会
研究活動情報
論文
- Reina Suzuki; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaBiological & Pharmaceutical Bulletin 48 4 457 - 462 2025年04月 [査読有り]
- Daisuke Kondo; Ruriko Suzuki; Ayako Matsumura; Hitomi Meguri; Masahiko Tanaka; Makoto Itakura; Naohide HirashimaEuropean Journal of Immunology 53 12 e2250360 2023年09月 [査読有り]
- Hikaru Teramoto; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaCells 12 14 1867 2023年07月 [査読有り]
- Hikaru Teramoto; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaBiological and Pharmaceutical Bulletin 45 4 547 - 551 2022年04月
- Yuki Horie; Toshiaki Arame; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaNeuroscience 458 87 - 98 2021年03月 [査読有り]
- Umi Okura; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaBiological and Pharmaceutical Bulletin 42 7 1230 - 1235 2019年07月 [査読有り]
- Yu Inoue; Seiji Hasegawa; Katsuma Miyachi; Takaaki Yamada; Satoru Nakata; Sari Ipponjima; Terumasa Hibi; Tomomi Nemoto; Masahiko Tanaka; Ryo Suzuki; Naohide HirashimaExperimental Dermatology 27 5 563 - 570 2018年05月 [査読有り]
- Maya Fujita; Takaki Yagi; Umi Okura; Jun'ichi Tanaka; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaBiological and Pharmaceutical Bulletin 41 5 786 - 796 2018年05月 [査読有り]
- Masahiko Tanaka; Tomomi Senda; Naohide HirashimaNeuroscience Letters 657 22 - 26 2017年09月 [査読有り]
- The dendritic differentiation of Purkinje neurons: unsolved mystery in formation of unique dendritesMasahiko TanakaCerebellum 14 3 227 - 230 2015年06月 [査読有り]
- Shin Nishikawa; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaMolecular Biotechnology 56 9 824 - 832 2014年09月 [査読有り]
- Miho Ikeya; Kiyoshi Yamanoue; Yuji Mochizuki; Hirofumi Konishi; Satoshi Tadokoro; Masahiko Tanaka; Ryo Suzuki; Naohide HirashimaBiochemical and Biophysical Research Communications 451 1 62 - 67 2014年08月 [査読有り]
- Yu Inoue; Seiji Hasegawa; Sadanori Ban; Takaaki Yamada; Yasushi Date; Hiroshi Mizutani; Satoru Nakata; Masahiko Tanaka; Naohide HirashimaJournal of Biological Chemistry 289 31 21451 - 21462 2014年08月 [査読有り]
- Ryo Ohashi; Shin-ichi Sakata; Asami Naito; Naohide Hirashima; Masahiko TanakaDevelopmental Neurobiology 74 4 467 - 480 2014年04月 [査読有り]
- Yoko Nishimura; Satoshi Tadokoro; Masahiko Tanaka; Naohide HirashimaBiochemical and Biophysical Research Communications 420 4 926 - 930 2012年04月 [査読有り]
- Masahiko Tanaka; Minami Asaoka; Yuchio Yanagawa; Naohide HirashimaNeurochemical Research 36 8 1482 - 1489 2011年08月 [査読有り]
- Mariko Miyata; Yasushi Kishimoto; Masahiko Tanaka; Kouichi Hashimoto; Naohide Hirashima; Yoshiharu Murata; Masanobu Kano; Yoshiko TakagishiJournal of Neuroscience 31 16 6067 - 6078 2011年04月 [査読有り]
- 培養神経細胞におけるGFPイメージングを用いた単一細胞レベルでのRNA干渉効果の解析田中正彦バイオイメージング 19 9 - 13 2010年06月
- Masahiko TanakaNeurochemical Research 34 12 2078 - 2088 2009年12月 [査読有り]
- Masahiko Tanaka; Shin-ichi Sakata; Naohide HirashimaNeuroscience Letters 462 1 30 - 32 2009年09月 [査読有り]
- Masahiko Tanaka; Yuchio Yanagawa; Naohide HirashimaJournal of Neuroscience Methods 178 1 80 - 86 2009年03月 [査読有り]
- Hidehiro Nomura; Toshihisa Ohtsuka; Satoshi Tadokoro; Masahiko Tanaka; Naohide HirashimaCellular Immunology 258 2 204 - 211 2009年 [査読有り]
- 田中正彦日本神経精神薬理学雑誌 27 3 135 - 140 2007年06月
- Masahiko Tanaka; Masahiro Kokubo; Tohru MarunouchiHistochemistry and Cell Biology 127 4 449 - 456 2007年04月 [査読有り]
- Masahiko Tanaka; R. Scott Duncan; Nathalie McClung; Jo-Ann S. Yannazzo; Sung-Yong Hwang; Tohru Marunouchi; Kaoru Inokuchi; Peter KoulenFEBS Letters 580 26 6145 - 6150 2006年11月 [査読有り]
- M. Tanaka; Y. Yanagawa; K. Obata; T. MarunouchiNeuroscience 141 2 663 - 674 2006年 [査読有り]
- M Tanaka; T MarunouchiNeuroscience Letters 390 3 182 - 186 2005年12月 [査読有り]
- Y Shimazaki; Nagata, I; M Ishii; M Tanaka; T Marunouchi; T Hata; N MaedaJournal of Neuroscience Research 82 2 172 - 183 2005年10月 [査読有り]
- 田中正彦Priming BioMedicine 2 23 - 35 加計学園細胞病理学センター 2005年03月
- M Tanaka; T MarunouchiNeuroscience Letters 353 2 87 - 90 2003年12月 [査読有り]
- M Tanaka; N Maeda; M Noda; T MarunouchiJournal of Neuroscience 23 7 2804 - 2814 2003年04月 [査読有り]
- 田中正彦神経化学 40 4 56 - 582 2001年12月
- M Tanaka; T Momoi; T MarunouchiDevelopmental Brain Research 121 2 223 - 228 2000年06月 [査読有り]
- M Tanaka; Y Kadokawa; Y Hamada; T MarunouchiJournal of Neurobiology 41 4 524 - 539 1999年12月 [査読有り]
- M Tanaka; M Sawada; M Miura; T MarunouchiNeuroscience 84 1 89 - 100 1998年05月 [査読有り]
- M Tanaka; T MarunouchiNeuroscience Letters 242 2 85 - 88 1998年02月 [査読有り]
- M Tanaka; T Marunouchi; M SawadaNeuroscience Letters 239 1 17 - 20 1997年12月 [査読有り]
- 大橋鉱二; 田中正彦; 澤田誠; 丸野内棣Tissue Culture Research Communications 15 4 221 - 227 日本組織培養学会 1996年
- M Tanaka; M Sawada; S Yoshida; F Hanaoka; T MarunouchiNeuroscience Letters 199 1 37 - 40 1995年10月 [査読有り]
- M Tanaka; S Yoshida; M Yano; F HanaokaNeuroreport 5 16 2049 - 2052 1994年10月 [査読有り]
- M Tanaka; A Tomita; S Yoshida; M Yano; H ShimizuBrain Research 641 2 319 - 327 1994年04月 [査読有り]
書籍
- Single-cell electroporation of siRNA in primary neuronal culturesSpringer, New York 2012年In: Controlled Genetic Manipulations (Morozov ed.), Neuromethods, Volume 65, pp. 129-139
- Role of a chondroitin sulfate proteoglycan PTPz in dendrite development of cerebellar Purkinje cellsResearch Signpost, Kerala, India 2007年In: Neural Proteoglycans (Maeda ed.), pp. 153-166
MISC
- 服部幸希; 望月雄司; 二宮里帆; 田中正彦; 鈴木亮; 平嶋尚英 生体膜と薬物の相互作用シンポジウム講演要旨集 41st 2019年
- Masahiko Tanaka; Tohru Marunouchi NEUROSCIENCE RESEARCH 55 S85 -S85 2006年
- 田中 正彦; 角川 裕造; 浜田 義雄; 丸野内 棣 日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集 21 597 -597 1998年12月
受賞
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 消化器官のグリア細胞・星細胞におけるカルシニューリンと細胞間相互作用の役割日本学術振興会:科研費(基盤C)研究期間 : 2019年 -2021年代表者 : 田中正彦
- 小腸の機能制御と恒常性維持における腸管グリア細胞とカルシニューリンの役割日本学術振興会:科研費(基盤C)研究期間 : 2016年 -2018年代表者 : 田中正彦
- 小脳プルキンエ細胞におけるリアノジン受容体を介した樹状突起形成制御機構の解明日本学術振興会:科研費(基盤C)研究期間 : 2013年 -2015年代表者 : 田中正彦
- 日本学術振興会:科研費(基盤C)研究期間 : 2010年 -2012年代表者 : 田中正彦小脳プルキンエ細胞が複雑かつ秩序立った形態の樹状突起を形成する分子機構を明らかにするために、培養プルキンエ細胞に対して様々な遺伝子のsiRNA を単一細胞エレクトロポレーションを用いて導入し、樹状突起形成への影響を調べた。リアノジン受容体、CaM kinase、myosin Vaが、それぞれ独自の働き方で樹状突起形成に関与することを発見した。また、単一細胞エレクトロポレーションを用いた遺伝子強制発現系や、小脳切片と分散プルキンエ細胞との共培養実験系を確立した。
- 日本学術振興会:科研費(基盤B)研究期間 : 2006年 -2008年代表者 : 平嶋 尚英; 田中 正彦; 田所 哲; 中西 守; 古野 忠秀生体では神経伝達物質やホルモンなど様々な細胞から多様な生理活性物質が分泌される。開口放出はその分泌機構の中で最も重要なものである。神経細胞では、神経伝達物質が細胞膜近傍のアクティブゾーンと呼ばれる特殊な構造から分泌されるが、このような構造が神経細胞以外の細胞で、存在しかつ機能するかどうか不明であった。我々はマスト細胞というアレルギー誘発物質を分泌する細胞では、ELKSと呼ばれるタンパク質が刺激後細胞膜付近に移動して、分泌を正に制御することを明らかにした。
- 日本学術振興会:科研費(萌芽)研究期間 : 2006年 -2007年代表者 : 平嶋 尚英; 田中 正彦ラット好塩基球株(RBL2H3細胞)は、細胞表面にIgE受容体をもち、この受容体DNP (dinitrophenyl)基を認識するIgEを結合させることによって、DNP基で修飾したCHO細胞を特異的に認識し、それに向かって分泌する系を構築した。CHO細胞にはあらかじめ分泌されたヒスタミンに応答するようにヒスタミン受容体(H1受容体)を発現させた。。 ヒスタミン受容体(H1受容体)を発現させたCHO細胞は、ヒスタミンに反応し、細胞内のCaイオン濃度上昇がおきることを確認した。 CHO細胞のDNP基修飾は、弱アルカリ性存在下に、DNBS(dinitro-benzene-sulfonic acid)と混ぜ、37℃でインキュベーションすることによって、細胞表面のアミノ基にラベルすることによって行ったが、細胞毒性が強くラベルできなかった。そこで、リン脂質であるホスファチジルエタノールアミン(PE)にDNP基を修飾し、CHO細胞の細胞膜に取り込ませる方法を試みた。その結果、細胞膜をほぼ均一にDNP-PE修飾できた。 そこで、あらかじめFura-RedをロードしたDNP修飾したヒスタミン受容体安定発現CHO細胞とDNP修飾をしていないヒスタミン受容体安定発現CHO細胞に対して、抗DNP-IgEを結合させたRBL2H3細胞を加えた。しかしながら、DNP修飾したCHO細胞において、RBL細胞から分泌されたヒスタミンによって細胞内のCa濃度上昇が見られた細胞は検出できなかった。 ラベルしたDNP量や細胞間のコンタクトの強度を考慮して再検討を行う必要がある。
- 神経幹細胞の最終細胞分裂に及ぼす細胞内外因子の効果日本学術振興会:科研費(基盤B)研究期間 : 2003年 -2004年代表者 : 丸野内 棣, 松下 文雄, 田中 正彦, 角川 裕造, 亀山 俊樹
- 日本学術振興会:科研費(若手B)研究期間 : 2003年 -2004年代表者 : 田中正彦これまでの我々の研究によって、小脳プルキンエ細胞の樹状突起が正常な形態に形成されるためにはコンドロイチン硫酸プロテオグリカンかつ受容体型チロシンポスファターゼであるPTPζのシグナルが働くことが必要であることが示されるとともに、PTPζシグナルの下流ではグルタミン酸トランスポーターであるGLASTの発現が制御されることが示唆されていた。そこで本年度は、PTPζ及びGLASTの役割を更に様々な角度から明らかにするために、以下の実験を行った。 PTPζ、そのコンドロイチン硫酸転移酵素、GLASTといった3つの遺伝子のノックアウトマウスにおいて、小脳プルキンエ細胞樹状突起の形態形成に異常があるかを調べた。その結果、3種類全てのノックアウトマウスにおいて、小脳皮質形成過程で少数のプルキンエ細胞が異常な方向に伸びる一次樹状突起を有していることが見出された。In vivoにおいてもPTPζ及びGLASTがプルキンエ細胞樹状突起の正常な形態形成に関与していることが示された。PTPζとそのコンドロイチン硫酸転移酵素のノックアウトマウスにおいては、細胞体の位置異常を起こしているプルキンエ細胞も見出された。しかしながら、成熟したプルキンエ細胞では現在までのところこのような異常は見られていない。 また、GLASTの機能抑制によってプルキンエ細胞のグルタミン酸刺激に対する応答性がどのような影響を受けるかを調べるために、小脳切片培養系におけるCaイメージング実験を行った。その結果、グルタミン酸トランスポーター阻害剤処理によって、プルキンエ細胞のグルタミン酸刺激に対する応答性が昂進することが示された。PTPζ及びGLASTの発現や機能が異常になった条件下では、プルキンエ細胞の神経活動にこのような異常が起こることが樹状突起の形態形成異常の原因になっていることが示唆された。
- 日本学術振興会:科研費(奨励A)研究期間 : 1999年 -2000年代表者 : 田中正彦本研究では、蛍光蛋白質GFP(green fluorescent protein)を利用した細胞標識技術を脳の切片培養系に応用し、脳の形成過程での細胞分裂や細胞分化に伴う形態変化を生細胞において連続的に観察する実験系を構築する。材料としては、研究代表者が長年その切片培養系の開発と応用を続けてきたラット及びマウスの小脳を用いる。本年度は本研究の後半として、新たなトランスジェニックマウスを利用した方法を開発するとともに、小脳形成における細胞間相互作用の動態解析を開始した。1.新たなGFP遺伝子発現法として、GFAPプロモーター制御下でGFPを発現するトランスジェニックマウスを導入した。このマウスから作製した小脳切片を顕微鏡下で維持し蛍光観察するための種々の条件検討を行った結果、前年度に明らかにした実験条件に加えて、切片に近接する実験器具の温度制御が特に重要であることを明らかにした。これにより、生きているバーグマン・グリア細胞やアストロサイトの形態変化等を連続的に観察することができるようになった。2.これらの方法を応用して小脳形成における細胞間相互作用の動態を解析することを目指して、Notch受容体や成長因子プレイオトロフィンが顆粒細胞の移動、プルキンエ細胞の発達、バーグマン・グリアの分化等に及ぼす影響の解析を開始した。これまでに、Notch受容体の活性化によりバーグマン・グリアの形態異常が生じることや、プレイオトロフィンのシグナル抑制によりプルキンエ細胞の発達が阻害されることを示す予備的実験結果を得ており、今後これらの変化の動的な解析を進める予定である。
- 日本学術振興会:科研費(基盤C)研究期間 : 1998年 -1999年代表者 : 角川 裕造, 田中 正彦, 浜田 義雄1.グリア細胞におけるNotch2の機能 Notch2変異ヘテロマウスを用いたNotch2遺伝子発現パターンの解析から、幼若なグリア細胞ほどNotch2の発現は強くまたBrdUの取り込み活性も強いことが示された。実際にNotch2シグナルを恒常的に活性化するNotch2細胞内領域のみの発現ベクターをグリア初代培養細胞で発現させたところ、BrdUの取り込みの増大が確認された。以上の結果からグリア細胞の分化、増殖にNotch2のシグナルが直接関与していることが明らかとなった。 2.脳の形態形成におけるNotch2の機能解析 Notch2ノックアウトマウスは中枢神経系の分化が起こる前のE10.5に致死となってしまうため、新規に開発した手法を用いてNotch2ホモ変異胚と野生型胚でキメラを作製しこれを解析した。その結果キメラ胚は胚性致死を免れ妊娠10.5日以降も発生を続けられることがわかった。ホモ変異胚でみられたアポトーシスはキメラ胚では観察されず、Notch2変異による細胞自律的な現象ではないことがわかった。Notch2を発現している多くの組織はキメラ胚で異常は認められなかったが、E10.5以降の間脳、中脳の蓋板にホモ変異細胞は参加できないことがわかり、蓋板形成にNotch2が必須であることが明らかになった。 蓋板形成におけるNotch2の機能を知るためにいくつかの遺伝子を調べたところ、Wnt-1、Mash1などの遺伝子発現がNotch2変異マウスでは異常になっていることが示された。Notch2がこれらの遺伝子をどのように制御しているかを知るために、活性型Notch2の発現ベクターをE9.5のマウス胚の蓋板領域に導入し、全胚培養を行った結果、Notch2シグナルの活性化によってWnt-1遺伝子の発現抑制が引き起こされることが明らかになった。今後はこのような手法を用いて蓋板形成におけるNotch2のシグナル伝達系を解析していくと共に、脳の形態形成における蓋板の機能を解析していく予定である。
- 日本学術振興会:科研費(奨励A)研究期間 : 1997年 -1998年代表者 : 田中正彦ラット小脳の切片培養系を用いて、顆粒細胞の発生段階特異的なアポトーシスへのinterleukin-1β converting enzyme(ICE)ファミリープロテアーゼ(カスパーゼ)の関与とその活性制御機構の解明を進めた。我々が確立したこの系では、培地中にinsulinやIGF-Iを添加しない場合に外顆粒層の顆粒細胞がアポトーシスを起こす。前年度の研究により、このアポトーシスへのカスパーゼの関与とその発現・活性化様式が明らかになった。今年度は本研究の後半として、CPP32(カスパーゼ-3)の活性化様式についての更なる解析及びカスパーゼの活性制御におけるphosphatidylinositol-3(PI3)キナーゼやMAPキナーゼの役割の解析を行い、以下のことを明らかにした。1. アポトーシスを起こしている顆粒細胞でのカスパーゼ-3の活性化をin situで調べるために、活性型カスパーゼ-3特異的抗体を用いた免疫組織染色とTUNEL法との蛍光二重染色を行った。その結果、アポトーシスを起こしている顆粒細胞の10-30%で活性型カスパーゼ-3が検出された。この二重陽性率は、in vivoの新生仔小脳においても同様であった。このアポトーシスの少なくとも一部にカスパーゼ-3が関与していることが示されるとともに、それ以外のアポトーシス機構が存在する可能性も示唆された。2.InsulinやIGF-Iがこのアポトーシスを防御する際のシグナル伝達にPI3キナーゼやMAPキナーゼの経路が関与しているかを調べるために、insulin存在下で各キナーゼの阻害剤を添加し、アポトーシスが誘導されるかどうかを見た。その結果、PI3キナーゼ阻害剤によってアポトーシスが誘導されたが、MAPキナーゼ阻害剤によってはアポトーシスが誘導されなかった。この発生段階の顆粒細胞内で生存を維持するようにカスパーゼが抑制される機構に、IGF-I受容体-PI3キナーゼを介するシグナル伝達経路が関与していることが示唆された。
- 日本学術振興会:科研費(奨励A)研究期間 : 1996年 -1996年代表者 : 田中正彦神経発生が進行する過程での発生段階特異的な神経細胞死の機構を解明するために、ラット小脳の切片培養系を用いて、外顆粒層と内顆粒層の顆粒細胞死及びその調節機構を検討した。TUNEL法及び蛍光色素を用いた色素排除法によって、外顆粒層と内顆粒層の細胞死を検出した。外顆粒層においては、培地中からinsulinを除去することにより、TUNEL法陽性・色素排除法陰性の細胞死(アポトーシス)が誘導された。一方、内顆粒層においては、insulinの有無に関わらず、色素排除法陽性・TUNEL法陰性の細胞死が見られた。蛋白合成阻害剤により、前者は抑制され、後者は抑制されなかった。以下、前者(外顆粒層でのinsulin感受性アポトーシス)について詳細に検討した。(1)TUNEL法と発生段階特異的マーカー蛋白に対する抗体染色との二重染色を行った結果、アポトーシス細胞の一部が増殖細胞マーカー(PCNA)を発現していたのに対し、増殖終了直後の顆粒細胞のマーカー(TAG-1)を発現しているものは皆無であった。(2)IGF-Iアナログは、insulinよりも低濃度でこのアポトーシスを抑制した。(3)ICE様プロテアーゼ阻害剤がこのアポトーシスを抑制した。アポトーシス条件で、ICEの発現量の増加は認められなかったが、ICE様プロテアーゼ活性の増加が認められた。(4)高濃度のK処理は、このアポトーシスを部分的に抑制した。以上のように、切片培養系を有効に活用することにより、発生中の小脳において顆粒細胞の発生段階に特異的な細胞死の機構が存在することが示された。外顆粒層での細胞死はアポトーシスの性質を有し、増殖中の細胞で特異的に起こるものであり、ICE様プロテアーゼが関与し、IGF-I受容体刺激により抑制されることが明らかになった。このアポトーシスの少なくとも一部はK非感受性であることが示唆された。内顆粒層で起こる細胞死の機構については、今後の課題として残った。また、他のICEファミリープロテアーゼの関与やその活性化機構も今後の重要なテーマの一つである。